[雑感145] 外国語ワーキンググループ(第1回)で話したこと
このたび、中教審初等中等教育分科会の専門委員を拝命することになった。外国語ワーキンググループの一員を務める。 中央教育審 […]


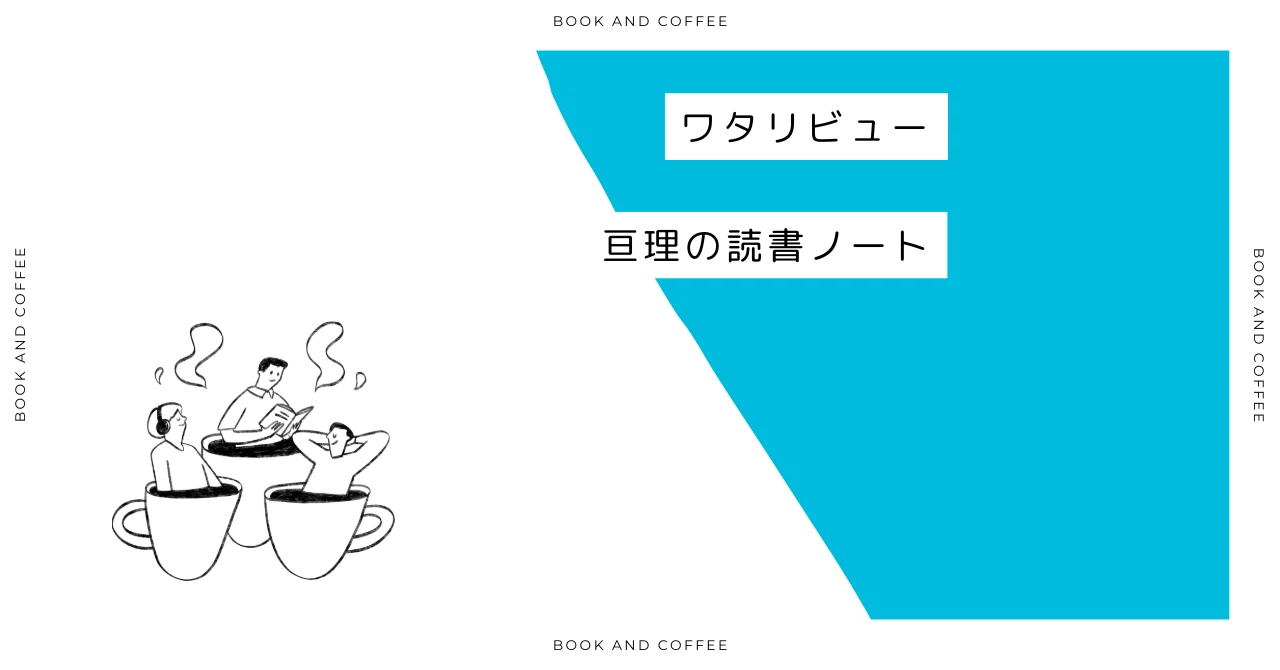
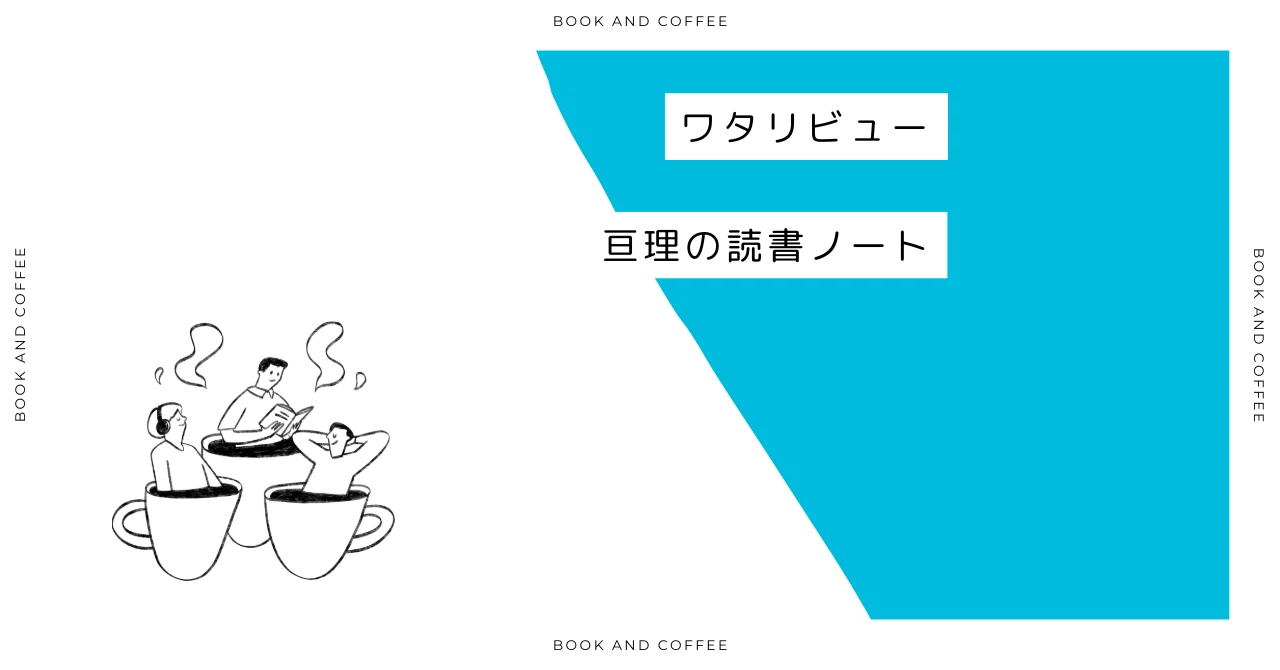
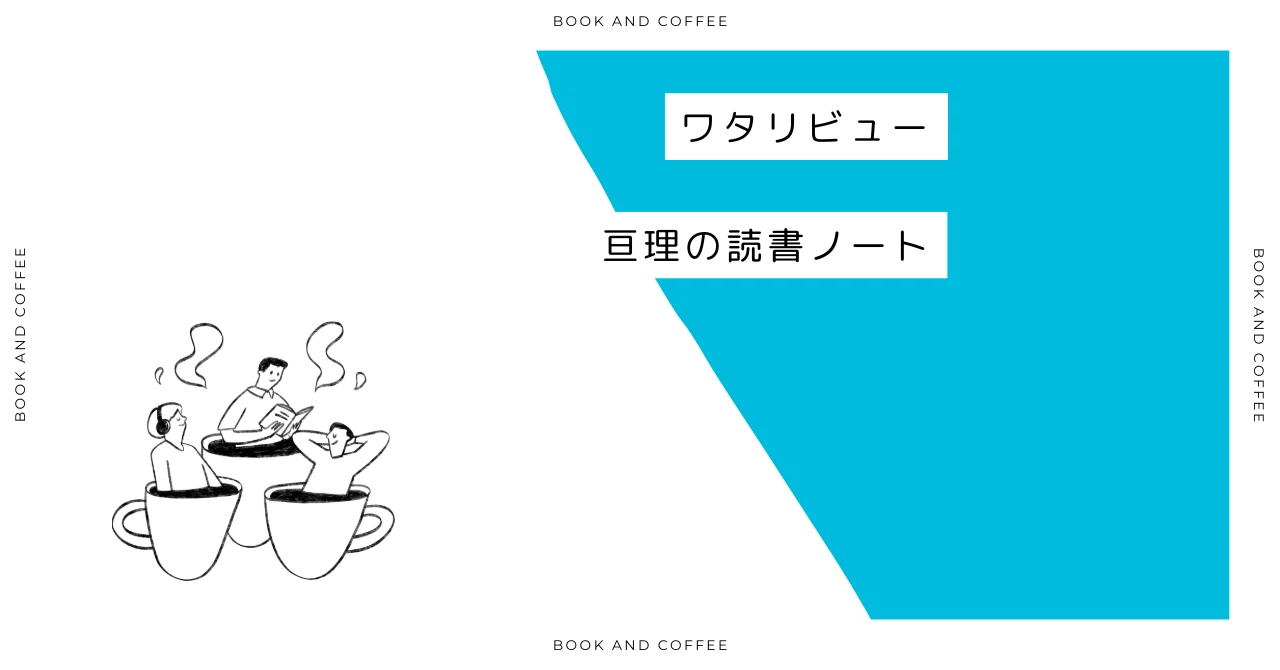
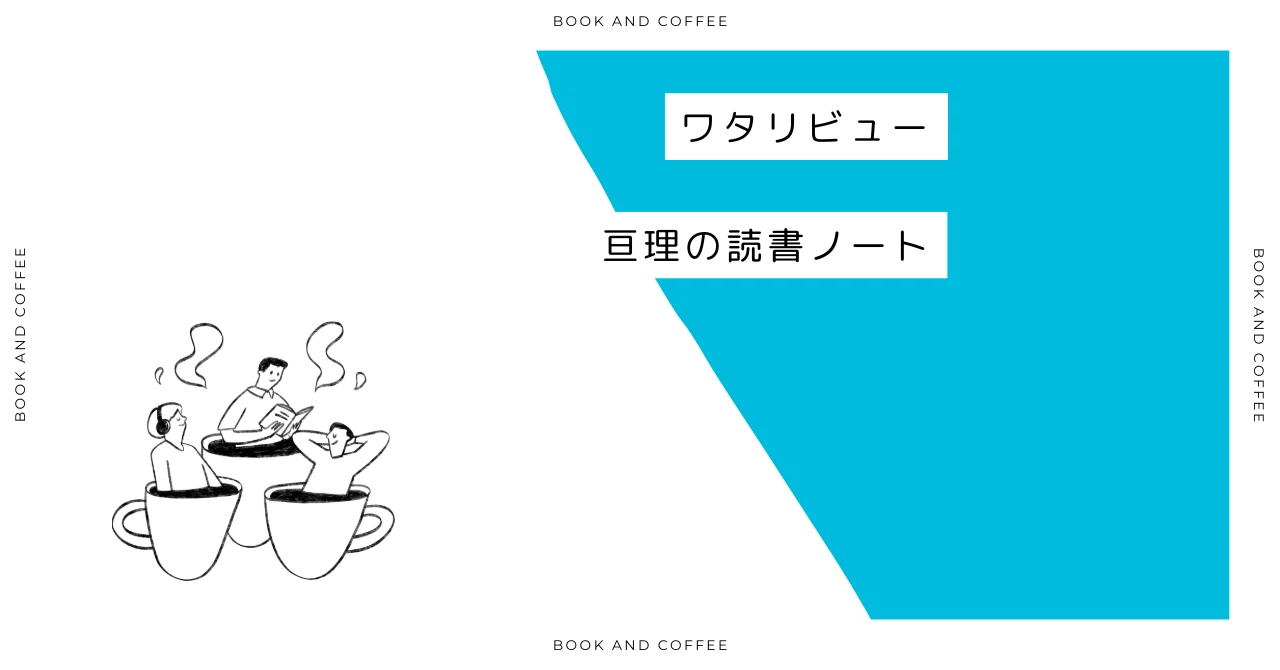
このたび、中教審初等中等教育分科会の専門委員を拝命することになった。外国語ワーキンググループの一員を務める。 中央教育審 […]
大修館書店『英語教育』2025年1月号の第1特集「次のカリキュラムに望むこと 先取りパブリック・コメント」に寄稿した記事 […]